どうもTfamilyです!!
もう少し、スローペースでやっていこうと思っていたこのシリーズですが、既に記事としては5つ目になります。
#5位で終わりにしようと思っていましたが、悩むところです。
これまでの記事をまだ読んでいない方はこちらからどうぞ。

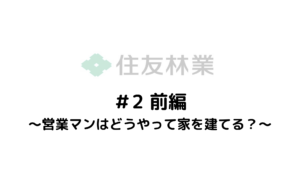
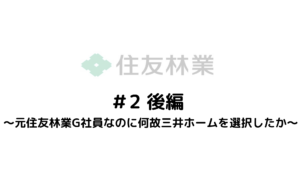
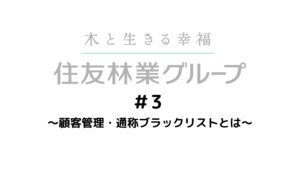
今回は見積りや施工品質は担当やエリアによって変わるのか否か。
お伝えできればと思います。
こんな方は是非参考にして下さい。
- 住友林業で建てるか迷っている
- 住友林業の施工体制ってどうなのか知りたい
- 良い担当に施工中は担当してほしいけど…
早速行ってみましょう!!
住友林業Gの見積・施工品質について
見積について

正直言って家造りで一番関心の高い部分はここだと思います。
住友林業では、見積を積算する優れた積算ソフトを活用しています。
これは何を意味するかというとエクセルや簡易的なソフトで見積を作成しているのではなくプラン作成ソフト等と連動させて誰が積算しても大凡同じ金額になるような仕組みになっております。
見積りは関心が高い事もあり、一番気になりますよね。
大手ハウスメーカーであればこのような仕組みはどこも採用していると思いますが、誰でも積算金額が同じになるのは安心できる事だと思います。
一方で細かい材料一つ一つを計上していくと明細が膨大になりますね。
住友林業ではある程度、大項目・中項目で見積書を作成しないと説明しきれない為、詳細の詳細まであえて表に出さない事も場合によってはあります。
こんなケースは
計画途中で窓をつけるのをやめた箇所があるとしましょう。
窓を取りやめたら当然窓の費用は無くなりますが、それと同時に増える項目も多々あります。

窓を無くしたら
- 外壁仕上げ面積が増える
- 外壁下地面積が増える
- 内部仕上げ面積が増える
- 内部下地面積が増える
- 断熱材が増える
等々、増える項目も結構あります。
そもそも入っている窓が標準仕様でお値打ちなものだったりすると、外壁がタイル仕上げの場合、逆に増えるパターンなんかも想定できるので是非とも確認して頂きたいものです。
どうしたらいい??
見積の明細、それすら出てきていない方或いは説明を受けていない方は是非ご相談下さい。

👇ご相談はこちらから
施工品質について

これは賛否両論ありますが、謳い文句ではなく現場サイドのありのままをお伝えしたいと思います。
ただ、私自身施工管理ではなかった為、身をもって体験していることではない事、ご容赦下さい。
住友林業では社外秘なる通称『赤本』と呼ばれる(今は呼び方違うかもしれません)明確な施工基準があります。
この中にはできてしまえば壊さない限り二度とみれない構造の作り方や納まりが事細かに示してあります。
その為、エリアにより多少の違いはあれど基本は誰が施工管理を担当しても同じになります。
もっと言うならば、実際施工する職人は住友林業の基準を理解していないと現場に入退場すらできません。
いろんな仕様が出てくるこの時代でも定期的に勉強会を開き技術の更新をしていきます。
その点では安心ですよね。
実際、施工管理をする生産担当は入社すると訓練校に全国から新人を招集し、家一軒を自ら建てます。私も入社当時は一軒建てました。
自らやる事で仕組みが体感できるのでとても良いと思います。
泊まり込みでこれをやるメーカーはなかなかないのではないでしょうか。
チェック体制は

施工が終盤になってくると検査もあり、厳しい採点を受けます。
ここでは施工店や職人も採点される為、皆一生懸命やりますね。
ただ、ここまでは仕上げに至る手前までの事です。
仕上げについて

仕上げに関しては、当然職人の腕も関わってきますがその材料にもよります。
例えばクロスだと機能性のある硬いクロスを広い面積に採用すると浮いてきたり、綺麗に貼り難かったりします。
また、我が家でも採用していますが壁をRにしたり変形壁・変形天井にすると仕上げに当然影響はあります。
職人の腕もそうですが、先ずはそのようなリスクのある材料の勉強も必要なのではないかと思います。
薄いクロスよりも分厚いクロスを選ぶようにする等していけばもしかしたらリスクを減らすことにつながるかもしれません。
もちろん硬くて薄いクロスを貼っても問題なかったお宅もあります。
一概には言えませんが、知っておくだけで仕様の打ち合わせも変わるのではないかと思います。
まとめ
- 見積りは誰が積算しても大凡同じ金額になる。※エリアにより仕様する材料が変わったりすることはあります。
- 施工品質は目に見えなくなる部分は安心安全の担保がある。※仕上げは施主側も知識をつけて打ち合わせする事が大事
如何でしたでしょうか。
人によって気になる部分とそうでない部分があると思うので、これが当たり前と言う定義がないのが住宅だと思います。
ただ、メーカー側では一律平等に良いものが提供できるよう努力する事はやめないでほしいですね。
それでは、次回はこのシリーズ最終回にしようと思います。
NEXT
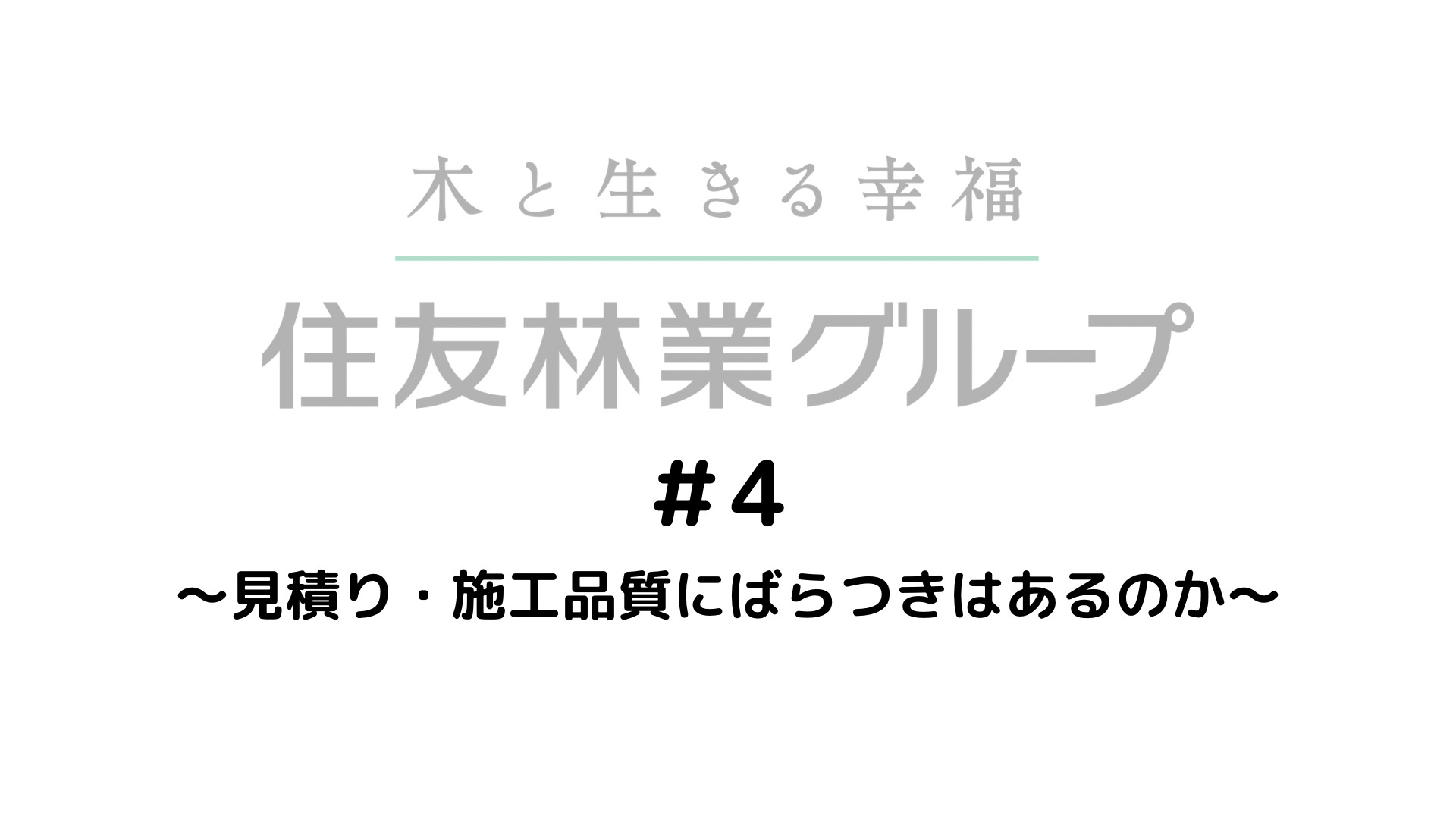
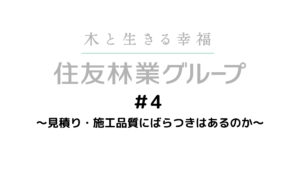
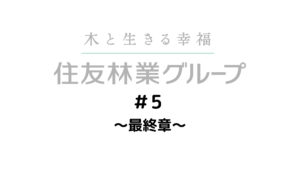
コメント