どうも!!
Tfamilyです!
シーズン1をご覧でない方はこちらの#1から是非ご覧下さい。
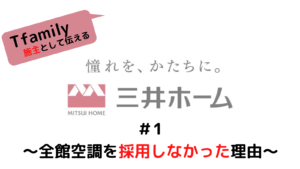
シーズン2の前回の記事はこちらです。
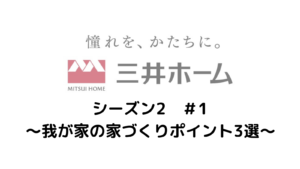
今回は家造りにおいて、意外と知らない事をお届けしていきたいと思います。
三井ホームに限らず、家造りにおいて知っておいた方がいい事をお伝えしますので是非引き出しを増やしてもらえたらと思います。
それでは早速いきましょう。
家造りで知っておいた方がいい事
皆さん家造りにおいて間取り・デザイン・機能はとても大事ですよね。
住み始めてからの暮らしにも大きな影響を与えます。
ですが、それ以外にも大切な事はたくさんあります。
カーポート&サイクルポート&テラス
皆さんカーポートや自転車用の屋根・テラス屋根を計画していたりしてませんか?
まだまだ車社会の地域も多く、必要なご家庭にはカーポートはとても重要ですよね。
また、お子さんがいるご家庭だと自転車置き場を設ける事もあるかと思います。
実際、私の住むエリアでは新築後(注文住宅に限らず分譲住宅でも)外構工事でカーポートを設けるお宅は非常に多いです。
但し、これには注意が必要です。
建坪率は大丈夫?
建坪率とは何か。
家造りをしている方なら理解できている人も多いと思いますが、
敷地面積に対する建築面積の割合の事を指します。
詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。

参照:SUUMO HP
何故、建坪率の話をしているかというとカーポートやサイクルポート・テラスも建坪率に算入されるからです。
屋根と柱で構成されるカーポート他は建築物とみなされ例外を除き建坪率の計算に入れていかなといけません。
建築物になるということは設置するだけで増築工事となります。
そもそも、建坪率一杯一杯で家を建てた場合、余った敷地にカーポートを設置しようとしても建坪率超過になり建築基準法上、違法になるケースがあるのです。
街を見渡すと建坪率を明らかに超過しているであろう建物は少なくありません。
おそらくそういったお宅は新築時の検査を問題なく終了し、引渡しを終えてからの外構工事で設置をしているのでしょう。
中には知らずに設置をしている人もいたりします。
違法な設置を行うと即座に咎められる事はなくても行政から是正指示が入ると正規の形に戻さないといけなくなります。
設置を考えている方はよく確認をしてから工事を行う事を推奨します。
防火指定は?
建坪率がクリアできたところで次なる確認事項は自身の家のエリアに防火指定がかかっているかどうかです。
日本全国防火規定があり、大きくは都市計画法により以下のように大別されます。
- 防火地域
- 準防火地域
- 法22条指定区域
こちらも詳しく知りたい方はこちらを参考にしてみて下さい。
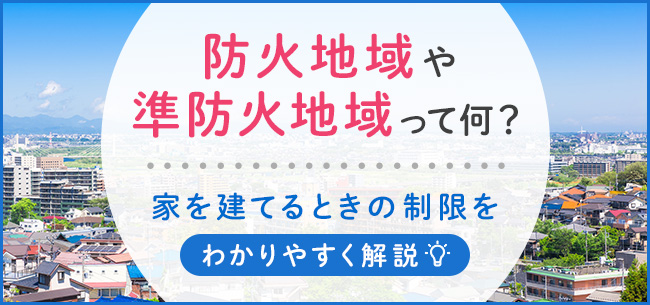
参照:SUUMO HP
先に述べたカーポートその他が建築物とみなされる場合、増築扱いの為、防火地域・準防火地域にあっては確認申請が必要になります。
防火指定がなくても10㎡以上の面積の建築物となる場合は確認申請が必要ですが、防火指定がある場合は1㎡でも増築すると確認申請が必要となります。
防火指定がない場合、サイクルポートであれば面積によっては確認申請は必要なくなるケースもありますがいずれにしても確認する事は必要です。
また、カーポートの商品としても防火認定が必要になる事も念頭にしておかなければいけません。
確認申請が必要となった場合、設置費用とは別に申請費用がかかります。
計画可能であれば家の建築と合わせて申請を出しておけば別途申請をすることもなくなり、出費を抑えることもできるので現在家造りをしている方で既にカーポートやサイクルポート・テラスを設置検討している方は是非建築するハウスメーカー等、住宅会社へ相談してみるといいと思います。
固定資産税は?
建築物ということは当然建物と同じように固定資産税がかかってきます。
これはご存知ない方も多いのですが、建築物というからには法律上、建物と扱いは同じです。
但し、こちらも条件があります。
- 3方が壁で囲まれている
- 基礎等で固定されている
- 用途が何か
等の条件によって課税対象になる為、確認が必要です。
一般的な柱と屋根からなるカーポートやサイクルポートは課税対象にならないケースが多いですが、テラスとなると上記の条件に当てはまる商品も多い為、こちらはよく検討する事をお勧めします。
実際何が対象になって、何が対象にならないのかの判断を私が決めているわけではないので詳しい説明はここでは控えますが、先ずは家を建てたハウスメーカーへの確認をする事が正確な答えが返ってくる方法だと思います。
リフォーム・エクステリア業界
今回は家造りにおいて知っておいた方がいい事をご紹介しました。
カーポートやサイクルポート・テラスの設置相談が梅雨時期もあってか多くなってきて今回紹介した事を知らない方が散見されたので記事に致しました。
というのも、実際設置する業者側は今回お届けした内容を知ってか・知らぬか遵守せず施工する事がまだまだ多いのが現状です。
施主側も法律を守る事を意識し計画をする事が大切です。
余談ではありますが、ある自治体では違法な施工に対してようやくメスを入れるとの話も上がっています。
ルールはある以上守りながら、正当な施工・計画を心がけてほしいです。
今回はここまで。
See You Next Time!!
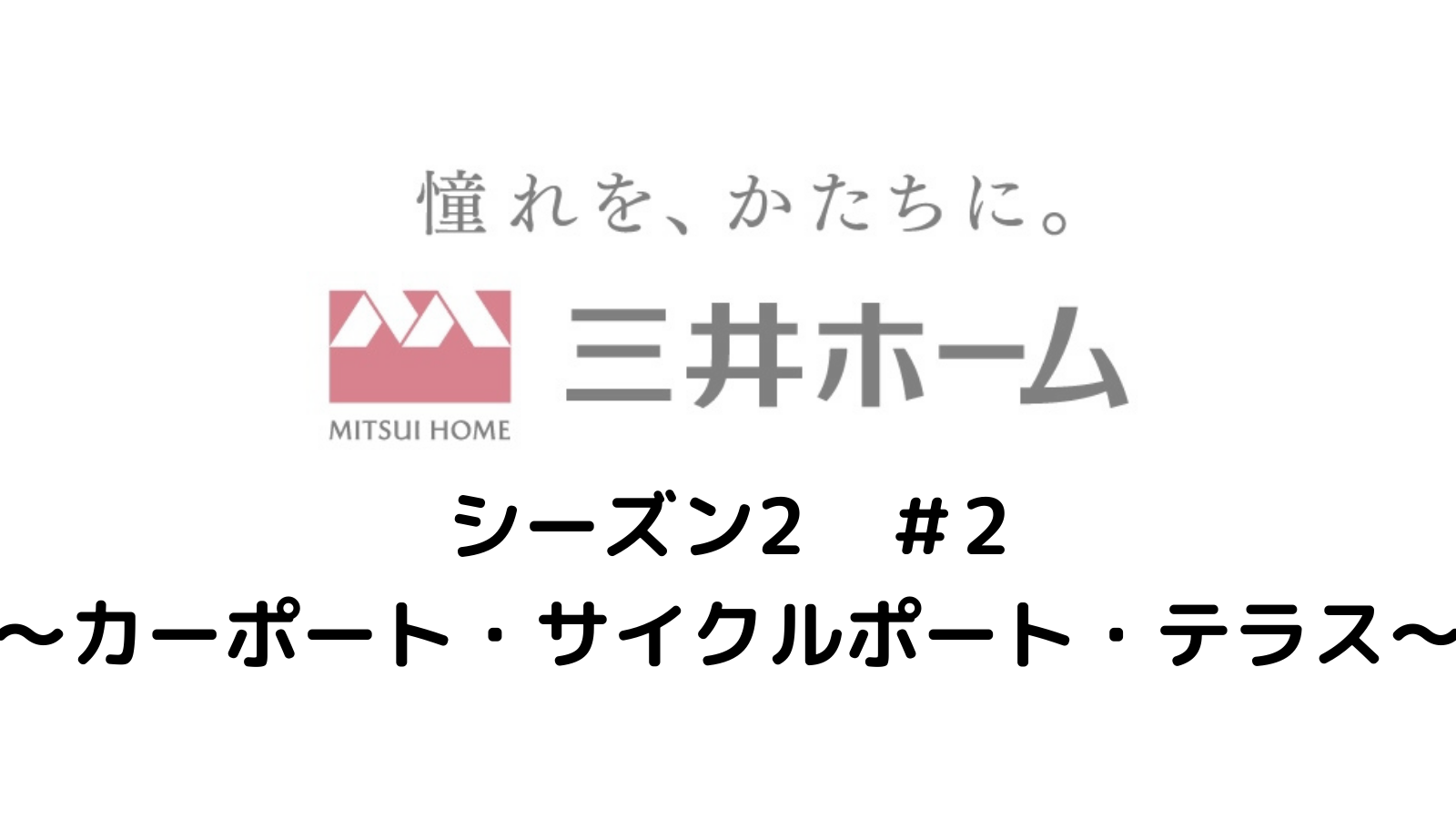
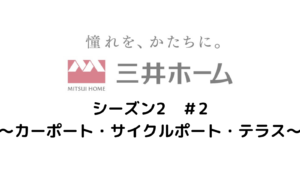
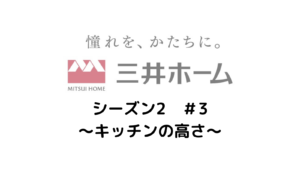
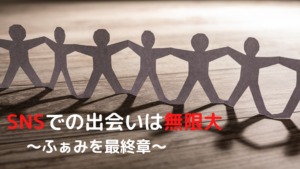
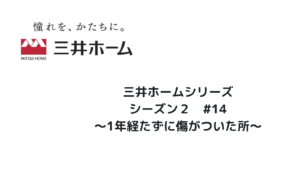
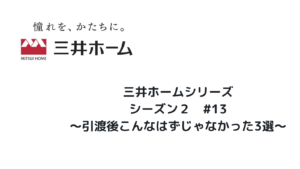
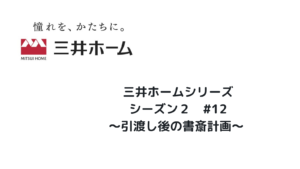

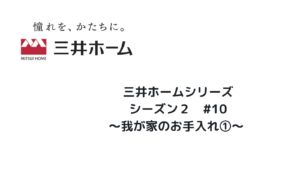
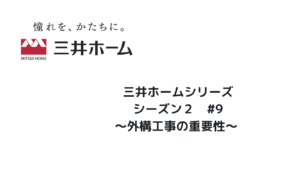
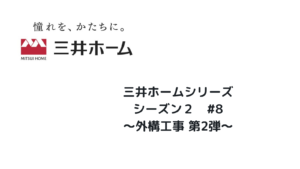
コメント